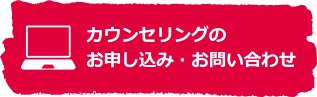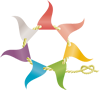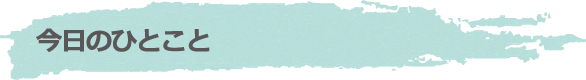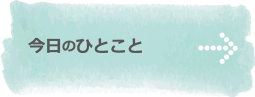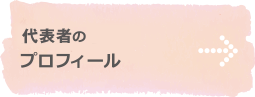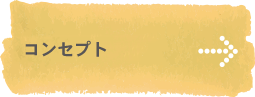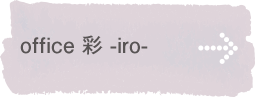記事一覧
-
療育のあり方
ここ最近、『療育』 という言葉をよく耳にします。 職業柄かもしれませんが、私自身も療育に関する相談を受けることが多いです。 『療育』 といっても 『集団療育』 や 『個別療育』 などさまざまです。 私は、カウンセリングの仕事の他に、未就学児の療育施設でも非常勤で仕事をしています。 そこで感じることは、お子さんに療育が必要な場合、「いかに早く、療育に繋がるか」
ここ最近、『療育』 という言葉をよく耳にします。
職業柄かもしれませんが、私自身も療育に関する相談を受けることが多いです。
『療育』 といっても 『集団療育』 や 『個別療育』 などさまざまです。
私は、カウンセリングの仕事の他に、未就学児の療育施設でも非常勤で仕事をしています。
そこで感じることは、お子さんに療育が必要な場合、「いかに早く、療育に繋がるか」 そして 「小学校に上がるまでに、どれだけ適切で充実した療育を受けられるか」 がとても重要で、それが、この先の学校生活や社会での生活に大きく影響してくるということです。
療育施設を利用されているお子さんは、早くて1歳半健診か3歳児健診で療育をすすめられたケースが多いです。
そして、集団療育が合っているのか、個別療育の方が良いのか、迷われる親御さんが多くおられます。
これについては、お子さんそれぞれの生育歴や環境、特性などによって違ってくるので、一言でどちらが良いとは言えません。
ただ、小さいお子さんは、個別療育から少しずつ集団療育に移行していかれる方が、親御さんもお子さんも無理なく進んでいけるのではないかなと思います。
私は、これまでたくさんのケースを見てきて、たくさんのお子さんとその親御さんに関わらせていただく中で、『家庭療育』 というものを考えました。
この 『家庭療育』 とは、療育支援に加えて、心理的な視点や育児サポートの側面も重要視しながら、一人ひとりのお子さんに、親御さんと連携しながら関わっていくというものです。
単に 『保育』 『療育』 だけでなく、『心理支援』も組み合わせて見ていけるのは、心理師である私の強みだと思っています。
「我が子が、健診で引っかかった。」
「療育をすすめられたけど、そもそも療育ってどんなことをするの?」
「子どもの癇癪に、どう対応すればいいのかわからない。」
「育児が、しんどくて、つらい。」
みなさん、さまざまな不安をお待ちです。
どうか、おひとりで悩ます、そして周りや行政の言葉に右往左往なさらず、ご相談ください。
お子さんにとって無理のない療育を、一緒にみつけていければと思います。
-
3/3 もう3月…
- 投稿日 :
- 2024-03-03 00:00:00
- カテゴリ :
- today's diary
- WRITER :
- chi.
早いですね、ほんとに…。 昨年末から、いつも以上に忙しい毎日で、とにかくその日その日を乗り切るのに必死な生活をしていました。 気がついたら、もう3月になっていました … 笑 3月は、私にとって、とてもとても大切で意味のある一か月です。 自分が生まれてきたこと、私を産んで育ててくれたこと、親子の絆、家族、自分のルーツ… などなど、毎年
早いですね、ほんとに…。
昨年末から、いつも以上に忙しい毎日で、とにかくその日その日を乗り切るのに必死な生活をしていました。
気がついたら、もう3月になっていました … 笑
3月は、私にとって、とてもとても大切で意味のある一か月です。
自分が生まれてきたこと、私を産んで育ててくれたこと、親子の絆、家族、自分のルーツ… などなど、毎年たくさんのことを考えさせられる時なのです。
今年こそは、どうか穏やかに、自分らしく過ごせますように。
-
悲しいニュース
このところ、偉大なアーティストの訃報が続いています。 人は誰でも、いつか必ず死を迎えることはわかっているけど、あまりに早すぎる死は悲しみが深すぎて受け入れられないです。 音楽の力がどれたけ大きいか、いまさらながら思い知らされています…。 いろんな場面で、たくさん勇気づけられました。 毎晩、泣いてばかりいた時は、少しだけ安心感をもらいました。 自分の胸の中にあ
このところ、偉大なアーティストの訃報が続いています。
人は誰でも、いつか必ず死を迎えることはわかっているけど、あまりに早すぎる死は悲しみが深すぎて受け入れられないです。
音楽の力がどれたけ大きいか、いまさらながら思い知らされています…。
いろんな場面で、たくさん勇気づけられました。
毎晩、泣いてばかりいた時は、少しだけ安心感をもらいました。
自分の胸の中にある思いを、その曲の詞に重ね合わせて、静かに口ずさんだりしていました。
好きな曲を聴くと、その曲を聴いていた頃に戻れるような気がします。
今日は、車の中で繰り返し 『愛は勝つ』 を聴いています。
自分の想いが実らなかった時、この曲と詞に励まされたことを思い出します。
優しい気持ちになれる曲。
ピアノのイントロを聴くと、涙が止まりません…。
残された私たちは、自分を大切に、一生懸命に生きていかなければいけませんね。
-
11月
- 投稿日 :
- 2023-11-01 00:00:00
- カテゴリ :
- today's diary
- WRITER :
- chi.
11月は、福祉に関しての重要な一か月です。 ・児童虐待を防止する ・女性の人権を守る・DVをなくす ・犯罪被害者に寄り添う その他にも、さまざまな活動や取り組みがおこなわれます。 困っている人、つらい思いをしている人、苦しみを抱えている人… 自分の周りにいないでしょうか? そんな人がいたら、自然にそっと手を差しのべられる人間であり
11月は、福祉に関しての重要な一か月です。
・児童虐待を防止する
・女性の人権を守る・DVをなくす
・犯罪被害者に寄り添う
その他にも、さまざまな活動や取り組みがおこなわれます。
困っている人、つらい思いをしている人、苦しみを抱えている人…
自分の周りにいないでしょうか?
そんな人がいたら、自然にそっと手を差しのべられる人間でありたいものです。
-
10/10 世界メンタルヘルスDAY
- 投稿日 :
- 2023-10-10 00:00:00
- カテゴリ :
- today's diary
- WRITER :
- chi.
今日 10月10日は、『世界メンタルヘルスDAY』 です。 私がメンタルヘルスの分野に携わって、もう20年近く経ちますが、ここ数年でようやく、やっと広く認知されてきたなぁ… というのが、正直な気持ちです。 認知されていくと、その分だけ、偏見や差別も顕著になってきます。 一人でも多くの人に理解を得られるよう、心理師として、責任ある対
今日 10月10日は、『世界メンタルヘルスDAY』 です。
私がメンタルヘルスの分野に携わって、もう20年近く経ちますが、ここ数年でようやく、やっと広く認知されてきたなぁ… というのが、正直な気持ちです。
認知されていくと、その分だけ、偏見や差別も顕著になってきます。
一人でも多くの人に理解を得られるよう、心理師として、責任ある対応と勤勉な姿勢で、これからも世に貢献していきたいと思っています。
『一人ひとりが、素直に自分らしく生きていけるように。』
それが、私の願いです。
カレンダー
< |
> |
|||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |